塾の復習テストや公開学力テストの後で、「やり方は分かっているんだけど、最後まで行きつかなかった。時間があれば解けたのに![]() 」という言い訳をぼんず君からよく聞きました。
」という言い訳をぼんず君からよく聞きました。
私の返答は「時間が足りないのは、ノロいから![]() 分かっているけど、時間不足で解けなかった、ってのは何の言い訳にもならないよ。もっと速く解けるようにならないと」と、うるさく言い続けました。
分かっているけど、時間不足で解けなかった、ってのは何の言い訳にもならないよ。もっと速く解けるようにならないと」と、うるさく言い続けました。
ぼんず君は元々、動きの遅いのんびりした子で、親が早く早くと急かすと、かえって焦って失敗するようなヘタレです。
「速く解く」と言われても、子どもはイメージできないので、テキストや公開学力テストを使って、各問題を何分で解く必要があるか、説明する必要があります。
復習テストの場合、小4以降のVクラスは問題数が異様に多くなるので、1問2分。公開学力テストの場合、小6は特殊ケースなので割愛しますが、小5までの場合は、前半と後半に分けて、さらに大問と小問で時間配分してみましょう![]() 計算テキストを毎日解く際にも時間を計ると良いです。
計算テキストを毎日解く際にも時間を計ると良いです。
公開の大問を3分で解くって、大変ですよ![]() 初見の問題はあっという間に3分が経ってしまいます。いかに普段のんびり解いているか実感できます。
初見の問題はあっという間に3分が経ってしまいます。いかに普段のんびり解いているか実感できます。
算数は特に体に時間を刻み込む練習が必須です。タイマーがあると便利です。分秒が正確に計れる電卓型がおすすめです。我が家はアマゾンで購入したタイマーを愛用していました。
時間を知らせる音がうるさいです。内部の配線の何かを切ると音が出なくなる裏技があるそうですが、動かなくなるんじゃ?と怖くて、私はやっておりません。
我が家は算数のテキストを解く時は、目の前に親が座り、1問ずつ計って解かせました。国語のテキストは1問20分で解かせました。
小6の夏~秋以降は、空き時間全て使って過去問を解き続ける時期がきます。タイマーはあった方が良いです。ぼんず君だけでなく、小6になると塾にタイマー持参のお子さんが増えます。
休憩時間に時間を計って勉強するのではなく、ただ単に「ピピピピ」とうるさく鳴らし続けるだけなのですが![]()





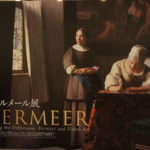


コメント